目次
心理学でいう嘘の定義とは
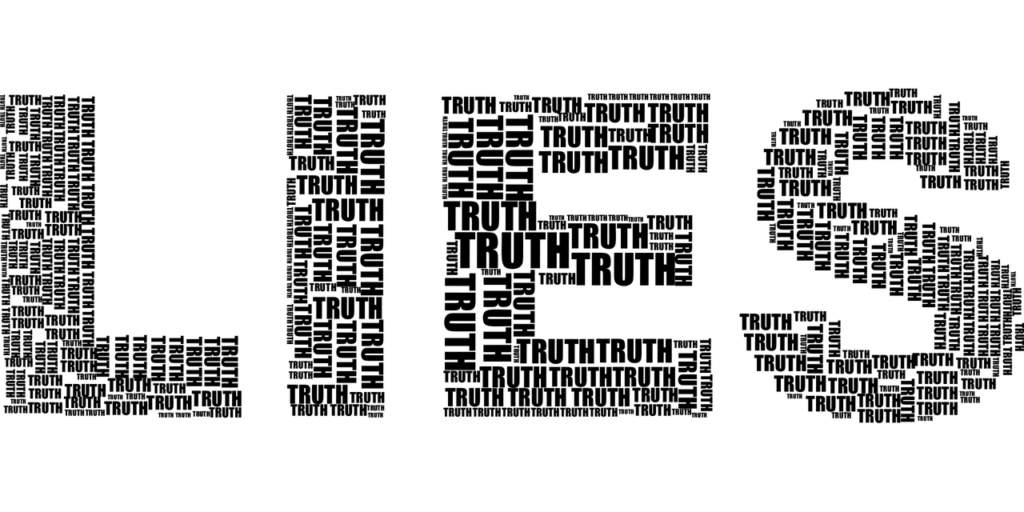
心理学でいう嘘の定義は「意図的にだます陳述をさし、単なる不正確な陳述とは異なる(『心理学辞典』有斐閣)」です。本記事でさす嘘も本当ではないと知りながら偽ることとし、思い込みや勘違いで真実ではないことを言う状態は含みません。意図的な嘘をつきはじめるのは、ウソとホントがわかる4~5歳の子どもからで、しかられないためや親の気をひくために使いはじめます。
嘘をつかれたくない女性の心理

ささいなことでも嘘をつかれると、悲しみや怒り、虚しさが湧きおこりつらくなります。時に気になり「嘘を許せない私は心が狭いのでは」と自分を責め、「また嘘をつかれるかも?」と拭えぬ不信感に苦しむでしょう。自分の存在を軽んじられた気持ちになり、嘘をついた相手を憎み心が荒れることも。こうした一連の傷つきをもう二度と体験したくないために、女性は嘘をつく男性を見抜きたいと思います。
嘘をつく男性のタイプ

嘘をつくタイプの人たちは、人への信頼感が低く、人は嘘をつくもので自分もだまされる可能性があると考えています。育ってきた中で、よい子でいようと大人の手をやかせないように頑張ってきたために、本当の欲求を抑えて嘘をついてきたことが大きな原因です。または、他人にあまり関心がなく、思いやりをあまり持てない人もいます。他人を信用しないタイプは、権力をほしがり、利益を得るためには人を陥れることもいといません。他人に興味がなく自分にしか関心がないタイプは、嘘をついても罪悪感を持たない場合が多いでしょう。
嘘をつく男性の心理

心理学者のウィルソンは嘘を5つのタイプにわけています。「自己保護のための嘘、自己拡大のための嘘、忠誠の嘘、利己的な嘘、反社会的、有害な嘘」です。
自分を守りたい
自己保護のための嘘では、自分を守りたい心理が働きます。真実を知られると怒られる、責められる、笑われるなどの自分に対する攻撃から身を守るための嘘です。浮気が発覚したにもかかわらず、していないと嘘をつくとき、本当のことを言えば怒られる、別れをきりだされるかもしれないと非難や罰への恐れの感情が根底にあります。
自分をよく見せたい
自己拡大のための嘘では、自分をよく見せたい心理が働きます。盛った話で人に認められたい、驚かれるようなホラを吹いて注目されたい欲求がある嘘です。女性にモテたくて経歴や年収を詐称する男性はこのタイプでしょう。ありのままの自分だと自信がない、不安が根底にあります。
相手を守りたい
忠誠の嘘では、大切な人を傷つけたくない、守りたい心理が働きます。人をかばうためにつく嘘や安心させるためにつく嘘、ハッキリ言わずにやんわりごまかす嘘、空気を読んでつく嘘などがそうです。ときに自分に不利益があろうとも、相手のために自分を犠牲にすることも。真実がわかれば相手が傷つくかもしれない不安があります。
利益を得たい
利己的な嘘では、利益を得たい心理が働きます。お金がほしい、仕事で有利なポジションにつきたいなど、自分のために人を欺く嘘です。恋愛では、結婚詐欺やデート商法、色恋営業、遊びのつもりなのに真剣だと伝える嘘などがあります。「自分は嘘をつかなくてはほしい物が手に入れられない」思い、自信のなさや恐れが根底にあります。
人を傷つけたい
反社会的・有害な嘘では、人を傷つけたい心理が働きます。復讐をしたい、困らせたい、罰を与えたいなど、いかに相手に有害であるかの観点で、相手または第三者に嘘をつく嘘です。深い人間不信や社会からも見捨てられるほど自分は価値がないと、自己信頼を失っている弱さが隠れています。抱えているのは強い不安や恐れです。
嘘をつくときの行動の特徴

人間は嘘をつくとき、真実を抑えこもうとして体は緊張状態になります。このとき体にさまざまな反応があらわれます。動物行動学者デズモンド・モリスは行動の信頼度を示しました。信頼度が高い順に、自律神経による体の変化、足の動きの変化、姿勢の変化、微妙な手の動き、意識的な手の動き、表情、言語です。
自律神経が体の反応にあらわれる
体が緊張状態のときは、交感神経が活発になっています。闘争ホルモンであるアドレナリンが分泌し、神経は敏感になり、筋肉は硬くなります。観察できる変化は、汗をかく、顔色が赤くなる、瞳孔が開く、呼吸が速く浅くなる、などです。本人の自覚として、口が渇く、尿意が頻繁におこる、便意が抑えられる変化がおこります。
具体的なしぐさや目線
貧乏ゆすりや足先の向きを反対方向に向けることが多くなります。姿勢は、胸が張りすぎて肩に力のはいった状態です。顔、特に口元や鼻を触るしぐさが増えます。目につきやすいのは、腕を組む、机の上の物を動かす、質問をしたときにネクタイをいじる、服のしわを伸ばす、机の上の物をそろえる動きです。逆に身ぶり手ぶりが減る場合もあります。目線は伏し目がちになるでしょう。
嘘をつくときの会話の特徴

嘘が態度やしぐさにでるのは個人差があり、聴覚情報のほうが嘘を見分けると、2003年の久留米大学心理学研究でわかりました。会話に注意すると嘘を見分ける可能性も高くなるでしょう。
会話がいつもより長いあるいは短い
嘘をつくと沈黙で「嘘がバレるのでは」と不安で、会話がとぎれずに長くなる傾向があります。聞いてもいないのに、理由やきっかけ、時系列を話したり「実は」「要するに」といった前置きが増えたりすることも。嘘をつくことに気をとられるあまり、あなたの話を聞けなくなり、つじつまが合わなくなるのを避けるため話が短くなる場合もあります。
質問返しが増える
質問されたとき、沈黙すると疑われるのではと考え、答える時間稼ぎのために質問返しをする場合があります。「今何してるの?」と聞かれると「今、ですか?今は……」とオウム返しをしたり「昨日の合コンどうだった?」と聞かれれば「なんで合コン?」「突然どうしたの?」と逆質問をしたりと、シンプルな即答が減ります。
逆ギレしたり泣いたりする
思わぬところで図星をつかれると、軽い混乱がおこり攻撃的になることも。信用されていないことに怒りを覚える、あるいは威圧して嘘を封じ込めたいときも逆ギレしがちです。もしくはうまい言い訳が考えつかない場合も、何と答えてよいかわからず高ぶった感情が涙や怒りにでます。
対処法は嘘をつかせないこと

嘘は、質問と返答の繰り返しで育成されます。最初に嘘をついてしまうと、次々に嘘を重ねて嘘が膨らむことをだれしも経験しているでしょう。一度嘘をつかれてしまうと、なかなか覆せません。まずは共感的な聞き役に徹し、相手にたくさん話をしてもらい情報を得ることが大切です。その後、少しずつ質問して外堀を埋めていきます。あえて沈黙を与えるのも効果的です。最後に証拠をだして、矛盾の説明を求めましょう。最初に証拠をだすと、はじめから嘘をつかせることになるので要注意。
男性が嘘をつくときの心理状態は不安と怖れ

男性が嘘をつくときの心理は、不安と恐れです。体は緊張状態になるため、落ち着きのない動作や会話が増えます。虚言癖や作為性障害などの嘘に慣れきっている場合を除き、普段と違うサインがみられるでしょう。対処法は不必要に嘘をつかせないこと。探る意図があると相手は余計にかたくなになるので、あなたがリラックスして、何を話しても大丈夫だよという雰囲気で向き合う方がずっとうまくいきます。この方法はあなたが幸せになるためにあります。相手をとがめたり懲らしめたりするためではないことを、心に留めておいてくださいね。











